中秋の名月(十五夜)といえば、お月見団子。
あなたは知ってましたか?十五夜に月見団子!その由来や意味は?
この日には、お団子をつくり、ススキを供えて、
月にお供えをして、美味しく楽しく団子を食べる!
そんな日なんですが、なぜ月にお供えをするのか?
なぜ団子を供えるようになったんでしょうか?
月見団子の起源、由来や意味を知りたい!
江戸時代からお月見の日に団子をお供えする習慣はあったといわれています。
収穫を祈り、収穫物であったお米のダンゴを使った事から
月見団子の由来だといわれています。
月にお供え物をするというのは、月が信仰の対象であったんですね。
この時期に収穫に感謝をしてお月さまに収穫物のダンゴをお供えするようになりました。
丸い団子は月を見たてて丸くしてありますが、地域に根差した様々な様式がお月見団子にはあります。
江戸時代では丸型で京都ではイモ型だったとも言われています、
お供えをする月見団子の数はいくつなんだろう?
お月見でお供えする月見団子の数にはある説があります。
十五夜には15個、十三夜には13個をお供えする。
これを略して、5個と3個という場合もあります。
その年の満月の回数分だけお供えする。
この場合、通常の年は12個、 うるう年の場合は13個になります。
お供えをする時の器について・・・
本来ですと三方に白い紙をしいてお団子を並べます。
三方がないという時は、お皿やお盆でも大丈夫です。
白い紙は、半紙やてんぷら色紙やなどで代用が出来ます。
月見団子の並べ方
①15個の場合
一段目:9個(3×3)
二段目:4個(2×2)
三段目:2個
※ここで注意したいのは、一番上の2個です。
正面から見て、縦に2個並ぶようにします。
横に2個並べると、仏事になってしまいます。
②13個の場合
一段目:9個(3×3)
二段目:4個(2×2)
③12個の場合
一段目:9個(3×3)
二段目:3個
お月見団子を作ろう!子供も作れる簡単レシピ
お月見団子
所用時間:約25分
お月見ダンゴにあう飲み物:麦茶、緑茶、ほうじ茶
材料
【約15個分】
だんご粉 120g
水 80~90cc
※だんご粉は、もち米、うるち米を同じ割合で混ぜた米粉です。
手順
1:だんご粉に水を混ぜ、耳たぶ程度のかたさになるよう、手でこねます。

2:こねた生地を15等分にし、手のひらで転がすようにして丸い形に作っていきます。

3:お湯を沸かして、沸騰したところへ丸めたダンゴを入れていきます。
ダンゴが浮き上がってきたら、そのまま2~3分煮ます。

5:冷めたらバットなどの上にあげて軽くうちわなどであおぐと、てりが出て綺麗な出来上がりになります。

・あんこや抹茶、きなこなど、お好みの味付けでお楽しみください。
・フルーツ缶と混ぜて、白玉ポンチなどにすると、また違ったおいしさが楽しめる、華やかで簡単なデザートになります。





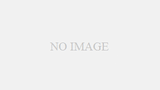

コメント